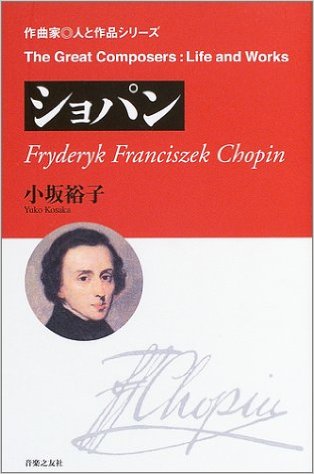第3章 ジョルジュ・サンド〜マジョルカ島逃避行、ノアンの館
傷つきやすい繊細な青年ショパンは、第2の恋人との破局で哀しみに沈んでいたころ、既に第3の恋人 との関係があったという。それが彼の人生を大きく狂わせ、否、彼の人生に大きな影響を及ぼした 男装の作家、ジョルジュ・サンドである。彼がはじめてサンドと会ったのは、超絶技巧のピアノで 楽壇の寵児としてもてはやされていたフランツ・リストの愛人である、ダグー夫人の夜会であった という。その時のサンドの第一印象を彼はこう書き記している。「なんて感じの悪い女なのだろう。 あれでも本当に女なのだろうか。それすらも疑いたくなる」黒色の服装に身を包み、ズボンをはき、 片時も葉巻を放さず、周囲に何人もの男をはべらせる男装の作家ジョルジュ・サンド。ジョルジュ・サンド というのは作家としてのペンネームで、本名はオーロール・デュパンという。一度は結婚して2人の子供 を産むが、退屈で想像力のない夫に愛想が尽き、自由の思想が支配する刺激的なパリの社交界へ身を 乗り出し、周囲の男を弄んではひんしゅくを買い、それを自らの楽しみとしていた女性。 周囲の評判は極めて悪く、しかもそれを全く気にも留めない神経の太さ。繊細でナイーブな 青年ショパンとは一見ちぐはくな結びつきに見える。
ショパンは初め、サンドに対して無関心を装っていたそうだ。否、私は実際、無関心に近かったのだ と考えている。しかし、サンドのショパンに対する視線には何か熱いものがあると直感したそうだ。 「僕がピアノを弾いている間中、あの人はあの澄んだ冷たく輝く瞳で僕の目の奥まで覗き込むように 見つめていた。あの人は、僕に特別な感情を持っている。ああ、オーロール・デュパン、なんて素敵な 名前なのだ。僕は彼女に惚れてしまった…」 最初に関心を示したのは、サンドの方だったようだが、その関心があまりにも強く、結局、ショパン もサンドの熱い視線に惹かれて、特別な感情が芽生えてしまったようなのだ。 そして2人は特別な関係として周囲の視線を避けるように愛を育んでいった。サンドのショパンに対する 気持ちは間違いなく本物で、この世でたった1人のかけがえのない恋人と考えていたようだ。しかし、 彼女にはそれまでの男遍歴とそれに伴うスキャンダラスな噂が取り巻き、サンドを独占しようとして いるとして、ショパンに決闘を申し込む輩まで現れたという。これ以上、2人の仲を噂されるのは、 神経過敏なショパンには耐えられなかっただろうし、サンドとしても周囲の目を気にせずに恋人のショパン と満ち足りた幸福の中で過ごしたいと考えていたようだ。
そこで選ばれたのが、スペインのバルセロナ沖に浮かぶ地中海の島「マジョルカ島」(island of Majorca)だった。澄み切った 青空の下、紺碧の地中海に浮かぶエメラルドグリーンのマジョルカ島は、年中温暖で地中海性気候特有の植物 が生い茂る南国の楽園、夢の別天地だった。2人がバラの花を咲かせる舞台としてこれほどのものはなかった。サンドは 2人の子供を連れて、ショパンとともにフランスからマジョルカ島への逃避行に出発した。これは 病身のショパンを思いやっての「転地療養」も兼ねていた。しかし、当初滞在予定だった島の中心地 の人々は、ショパンの病魔を恐れ、街から離れるように命じたそうである。仕方なく、ショパン、サンド 一行は、島の中心地から十数キロも離れた山奥の回教寺院である、ヴァルデモーザ(Valdemosa)の僧院に移り住んだ。 この僧院は既に廃墟と化しており、石造りで体に冷え、これも彼の健康を急速に悪化させる原因と なった。例年は温暖で、北アフリカの趣の漂うこのマジョルカ島は、その年の冬(1838年-1839年に かけて)に限って、本来雨季であるにせよ雨量が多く、湿りがちで寒く、ただでさえ病弱なショパンの健康を著しく悪化 させていったという。
ある日、ジョルジュ・サンドが2人の子供を連れて山を降り、島の中心部へ買い出しに出かけたまま、途中から 大雨が降り、夜になっても帰って来ないことに不安と恐怖を抱いたショパンは、やがて、サンドも2人の子供も 濁流に飲み込まれて死んでしまったのだと思い、幻覚に襲われながらピアノに向かって絶望を吐き出していた。 土砂降りの雨の中、サンドと2人の子供が帰ると、ショパンは「もう僕はあなたたちが死んでしまった ことを知っている」というようなことを言ったと伝えられている。その時の状況を振り返ってサンド は後にこう述べている。「…彼は一種の静かな絶望に陥っていた様子で、涙を流しながら素晴らしい プレリュードを弾いていました。その夜、僧院の屋根に音を立てて落ちていた雨のしずくは彼のイメージ と音楽の中で、天から彼の胸に落ちる涙に変わっていたのです。」 これが「雨だれの前奏曲」だったかどうかまでは分からないが、僕の感覚では、第4番ホ短調 や第6番ロ短調の方が曲の雰囲気がその状況に近いと感じる。
しかし例年にない雨量の多さと寒さで彼は健康を蝕まれていき、島の滞在そのものが不可能である ことを悟ったサンドは、瀕死のショパンを抱え、島を後にした。マジョルカ島へのこの逃避行が なかったら、ショパンはあと少なくとも10年は長生きしたというショパン研究家もいるという。 ことの真偽はともかくとして、それまでとそれ以後とで彼の健康状態は比べようもなく、いかに この逃避行が彼の寿命を縮めたか、それは推し量ることすら不可能だ。 私は今、年老いた大作曲家ショパンがどんな円熟の作品たちを創作し得たのか、それが知りたくて 仕方がない。ショパンを専門に研究している人の生の意見が聞いてみたいと思う次第である。
ともあれ、フランスに無事たどり着いて静養をしたショパンは、小康を得て、以後30代の時期に 次々に傑作を生み出すことになる。1840年からサンドとの破局を迎える1847年までの7年間、ショパンは 基本的には、夏はノアン(Nohant)の館(ジョルジュ・サンドの相続した大邸宅)で過ごし、冬はパリに出るという 生活を送った。ジョルジュ・サンドは愛するショパンを金銭的に面倒を見、彼が本業の作曲に専念 できる環境を整えていた。作品番号で言えば、ポロネーズ第5番嬰ヘ短調Op.44からポロネーズ第7番 変イ長調Op.61「幻想」あたりまでがこの相対的安定期の作とされている。次第に作品の規模が大きく なり、構成的にも和声的にも円熟味を増してきたのもこの頃からである。作品44〜61までの主だった 名曲としては、バラード第3番、第4番、スケルツォ第4番、幻想曲へ短調、バルカローレ、英雄 ポロネーズ、ノクターン第13番、ピアノソナタ第3番、それに美しいマズルカの数々などがある。
サンドのショパンに対する愛は紛れもない真実の愛であり、その献身ぶりはそれまで数々の男遍歴を 作ってきた「飛んでる女」のイメージからは想像もできないほど、優しさがこもっていたようだ。 「私はある人のために悩む必要がある。悩み疲れきったある人のために、母のような愛情を育んでいく 必要がある。」と彼女は書き残しているようだ。
しかし彼の心の中は決して平穏ではなかった。ジョルジュ・サンドという女性はショパンと出会う までは次々に男遍歴を作り、それを小説にして発表してしまうような性格の女性である。1ヶ所に じっとして一つの物事に集中するタイプではなく、常に新しいもの、刺激的なものを追い求める 女性である。そうしたいわゆる 「遊び心」も働いて、自宅に大勢の男を招いては思わせぶりな態度をとり、それが原因で、ショパンの サンドに対する猜疑心と嫉妬が大きく膨れ上がっていったのである。
ショパンは1人の女性を一途に思いつづけるという、真面目な恋愛しかできない純情派で、一方のサンドは エネルギッシュで、会った男全員に開けっぴろげな態度をとり、誘惑をする浮気派である。ショパンは 一極集中型で、サンドは多極分散型。サンドにしてみれば、ショパンの自分に対する愛情の強さを知って いて、それを確かめる目的で、他の男にも思わせぶりな態度を取っていたのかもしれない。そうすることに よってショパンの心を自分の方に一層ひきつけようという意図が彼女にはあったという解釈もできる。しかし ショパン本人にとってみれば、それは精神的苦痛でしかなかった。初めのうちはお互い、この世の誰よりも愛し 合っていた仲ではあるが、その恋愛観、愛情表現のあり方があまりにも違っていた。そういう2人の 感情の行き違いを考えると、この2人の関係がマジョルカ島への逃避行以来8年間も続いたこと自体、 不思議に思えてくる。
1845年を過ぎた頃から、ショパンとサンドの不協和音は次第に深刻なものになっていく。そこにはサンドの2人の 子供が大きく関与している。上の息子モーリスは、ショパンの存在を面白く思っていなかったようで、 サンドの側に回って、何かにつけてショパンを非難する態度を取った。一方、下の娘ソランジュは サンドと別々に暮らした期間が長く、サンドに対して常に反抗的で、ショパンの気を引こうとしていた。 こうして、サンド・モーリス VS ショパン・ソランジュという対立の図式ができあがって、サンドと ショパンの間には深い亀裂が入ったのである。さらにサンドは、多くの愛人を持つ未亡人と年下の貴族 の恋の物語「ルクレチア・フロリアーニ」を小説にして発表し、これが決定的な破局の原因と考える 人も多い。この小説に登場するカルロという青年貴族は明らかにショパンをモデルにしており、極めてエゴイスティック な男性として描かれているからだ。既にサンドはショパンの猜疑心と嫉妬深さにほとほとあきれ果てていて 、半ば彼女は彼を強引に突き放す形での破局となったようである。
それからの3年間のショパンは魂の抜けたいわば亡霊のような人間として描写されている。1848年、 ショパンの生活の拠点だったフランスでは二月革命による騒動が起こり、逃避を余儀なくされた。 結局、彼は弟子の1人だったジェーン・スターリング伯爵夫人の招待により、 イギリス・スコットランドを演奏旅行することになる。 既に魂の抜け殻となっていた彼は、既にあらゆる物事への情熱を失っていた。 「僕は草や木のようにぼんやり月を送っている。僕は、じっと生涯の終わりを待っているのだ。 僕の心を、僕はどこへ使い捨ててしまったのか。故郷でどういう歌が歌われていたか、もう 思い出せないくらいだ。」 彼を熱愛するジェーン・スターリングの過剰な愛情をうっとうしく思いながら、彼は、エジンバラの宮廷や ヴィクトリア女王の前で、最後の気力を振り絞って御前演奏会を行っていた。 すでにフランスを離れることにより多くの教え子を失っていた彼は、再び収入面の問題を抱えていたようだ。 結局、イギリス・スコットランドへの演奏旅行は芳しい成果もなく、そこでの厳しい 気候と過酷な演奏スケジュールが彼の健康をさらに蝕み、気力も体力も抜けたボロボロの状態でパリに戻り、 孤独の病床についた。
そして1849年10月17日、病床のショパンはポーランド時代からの旧友だったデルフィーナ・ポトツカ 夫人や姉のルドヴィカ(Ludwika Jedrzejewiczowa)に看取られながら、39歳の若さで帰らぬ人となった。 そのとき、彼のデスマスクとともに、左手が模られた。その石膏は今もワルシャワ・ショパン協会に 収められている。
彼の遺言通り、葬儀には彼の作曲した「葬送行進曲」と敬愛する作曲家モーツァルトの「レクイエム」 が演奏され、厳かに行われたという。そして彼の心臓は姉ルドヴィカの手によって祖国ポーランドに 持ち帰られ、ワルシャワの聖十字架教会(the Holy Cross church)の柱の奥深くに埋められ、安置された。 ショパンの遺体は、 パリ北方のモンマルトルにほど近い「ペール・ラシェーズ墓地(Pere-Lachaise cemetery) 」の一画に 埋葬され、ポーランド出国の際、友人達から受け取った祖国ポーランドの「土」がかけられたという。 ショパンの横顔をかたどったレリーフのある墓石の上の、悲しみに打ちひしがれ低くうなだれる天使の像が、彼の 波乱に満ちた不幸な生涯を象徴しているようだ。ピアノの詩人、天才を慕い、今日もそこを訪れる人は多い。
思えば、誰よりも 祖国ポーランドを愛し、望郷の念に駆られながらも、20歳で祖国を離れてからついに一度も祖国の 土を踏むことがかなわなかった彼にしてみれば、せめて死んだ後は、自分の心だけは祖国ポーランド とともにありたいと願っていたことは、彼の作曲の姿からもうかがい知ることができる。 彼がはじめて曲を書いたのは7歳のときで、それはト短調の短いポロネーズだった。そして、彼の 絶筆となったのは、病床で書き上げ、ついに一度もピアノで音にすることができなかったと 言われるへ短調のマズルカ(Op.68-4)だった。彼の創作の最初と最後がはからずも彼の祖国 ポーランドの民族舞曲であったことは単なる偶然ではなかったように思えてくる。彼の故郷を想う 気持ち、それは彼の孤独感と密接に結びついていた。そのことは彼の作曲した50曲を超えるマズルカ がなにより物語っている。